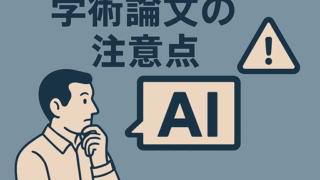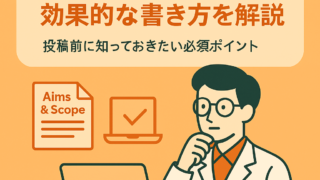| 掲載記事数 |
|---|
| 114記事 |
Crossrefは、DOI(デジタルオブジェクト識別子)を利用して、学術論文や研究データの管理、アクセス、引用を効率的に行えるように支援するだけでなく、さまざまなサービスを提供しています。これらのサービスにより、研究者、出版社、図書館などの学術コミュニティが情報の発見と共有を効率化し、研究活動全体の質を向上させることができます。
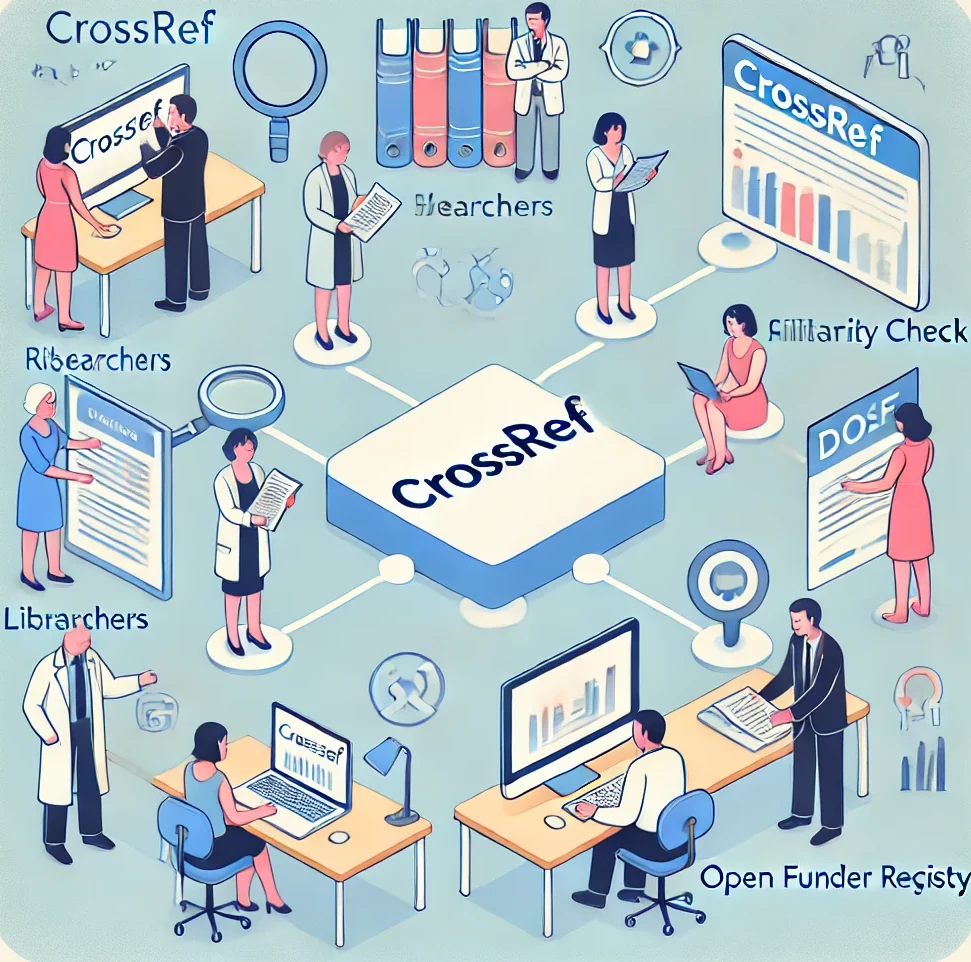
目次
- 1. Crossrefとは何か?その基本的な仕組みと役割
- 1.1. Crossrefとは
- 1.2. Crossrefの起源と歴史
- 1.3. CrossrefによるDOIの付与とその重要性
- 1.4. 研究者や図書館にとってのCrossrefの必要性
- 2. Crossrefのサービス一覧
- 2.1. Content Registration:コンテンツ登録
- 2.2. Grant Linking System :研究資金の連携
- 2.3. Metadata Retrieval:メタデータの取得
- 2.4. Open Funder Registry (OFR):研究助成機関の情報管理
- 2.5. Reference Linking:参照リンク
- 2.6. Similarity Check:類似性チェック
- 2.7. Cited-by:引用元
- 2.8. Metadata Plus:メタデータプラス
- 2.9. Event Data:イベントデータ
- 2.10. Crossmark:クロスマーク
- 3. 出版社にとってCrossrefの活用方法
- 3.1. DOI登録による著作物の利便性向上
- 3.2. CrossCheckで守る出版倫理
- 3.3. Crossmarkで論文の信頼性を高める
- 3.4. Open Funder Registryで研究資金の透明性を向上
- 3.5. Similarity Checkで盗用防止と出版倫理の維持
- 3.6. 出版業界全体におけるCrossrefの採用率
- 4. まとめ
- 5. 参考文献
Crossrefとは何か?その基本的な仕組みと役割
Crossrefとは
Crossrefとは、学術出版において研究論文やデータセットに対してDOI(デジタルオブジェクト識別子)を付与し、そのメタデータを管理する国際的な非営利組織です。
DOIを通じて、学術資料をオンラインで一意に識別し、永続的なリンクを提供することで、研究者や学術機関が研究成果を効率的に管理し、世界中の学術コミュニティと情報を共有できるようにサポートしています。
また、CrossrefはDOIの付与だけでなく、盗用防止のためのSimilarity Checkや、研究成果の引用数を追跡するCited-by、研究資金提供者を特定するOpen Funder Registryなど、学術出版や研究活動を支援するさまざまなサービスを提供しています。これらのサービスにより、学術情報の信頼性やアクセス性が向上し、研究活動の質を高めることができます。
Crossrefの起源と歴史
Crossrefは1999年に設立され、学術出版社、研究機関、図書館が協力してDOIの普及を推進することを目的として発足しました。
設立以来、CrossrefはDOIの標準化とメタデータ管理を通じて、学術コミュニケーションの改善に寄与してきました。現在では、世界中の何千もの学術機関がCrossrefに加盟し、学術情報の信頼性とアクセス性の向上に貢献しています。
CrossrefによるDOIの付与とその重要性
DOIは、研究論文やデータセットに対して一意の識別子を付与することで、インターネット上での学術資料の検索や引用を容易にします。
DOIを通じて、学術資料はオンラインでの永続的なアクセスが保証され、リンク切れなどの問題を防ぐことができます。これにより、研究者は自分の成果を広く共有し、他の研究者からの引用を促進することができます。
研究者や図書館にとってのCrossrefの必要性
Crossrefは、研究者や図書館にとって不可欠なツールです。
研究者は、DOIを利用することで、学術論文の管理、引用、参照を効率化できます。また、図書館はCrossrefを活用することで、学術資料の信頼性を確保し、利用者に対して最新かつ正確な情報を提供することが可能になります。
Crossrefのサービス一覧
Crossrefは、DOIの付与だけでなく、さまざまな学術出版支援のサービスを提供しています。以下は、Crossrefが提供する主要なサービスの一覧です。
| サービス名(英語) | 主なサービス | サービスの概要 |
|---|---|---|
| Content Registration | コンテンツ登録 | 学術論文やデータに一意のID(DOI)を付け、管理できるようにするサービス |
| Grant Linking System | グラント・リンキング・システム (研究資金の連携) | 研究に使われたお金とその成果を結びつけ、誰がどの研究に資金を提供したかを明確にするサービス |
| Metadata Retrieval | メタデータの取得 | 論文やデータに関する詳細な情報(メタデータ)を簡単に取得できるサービス |
| Open Funder Registry | 研究助成機関の情報管理 | 研究を支援する団体や組織の情報をまとめ、簡単に探せるようにするサービス |
| Reference Linking | 参照リンク | 論文内の参考文献とリンクをつなげ、他の論文へスムーズにアクセスできるサービス |
| Similarity Check | 類似性チェック | 論文が他の文献とどれだけ似ているかをチェックし、不正を防ぐためのサービス |
| Cited-by | 引用元 | 自分の論文が他の研究にどれだけ引用されているかを確認できるサービス |
| Metadata Plus | メタデータプラス | メタデータ管理の機能をさらに充実させ、大量のデータ処理ができるサービス |
| Event Data | イベントデータ | 研究がソーシャルメディアやニュースでどう話題になっているかを追跡するサービス |
| Crossmark | クロスマーク | 論文が更新や修正されたときに、その情報を読者に知らせるためのツール |
これらのサービスは、学術情報の流通や管理において非常に重要な役割を果たしており、研究者や学術機関が効率的に情報を扱うための強力なツールとなっています。
次に、それぞれのサービスについてもう少し詳しく説明します。これらのサービスがどのように活用され、学術コミュニケーションを支えているのかをご紹介します。
Content Registration:コンテンツ登録
Content Registration(コンテンツ登録)サービスは、学術コンテンツに対してDOIを付与し、そのメタデータを管理する機能を提供します。これはCrossrefの主要なサービスの一つであり、このサービスにより、学術資料の信頼性と発見性が向上し、他の研究者がコンテンツを容易に見つけて引用することが可能になります。
Crossrefのメンバーになると、システムからプログラムを介して自動的に登録、もしくはWEB上から手作業でメタデータを登録・更新することができます。
Grant Linking System :研究資金の連携
Grant Linking System(グラント・リンキング・システム)サービスは、研究資金提供者が資金提供に関連するメタデータを登録し、DOIを通じて研究成果と資金提供の関係を明確にするためのサービスです。
このサービスを利用することで、研究成果の透明性が向上し、資金提供者、研究者、出版社がそれぞれの役割を果たす際の効率が高まります。
Metadata Retrieval:メタデータの取得
Metadata Retrieval(メタデータの取得)サービスでは、Crossrefのメタデータを分析・取得し、研究活動に活用することができます。
DOIに関連するさまざまな情報(タイトル、著者、資金提供者、引用など)が含まれており、REST APIを介してこれらのデータにアクセスすることが可能です。すべてのCrossrefメタデータはオープンで、誰でも自由に利用することができます。
Open Funder Registry (OFR):研究助成機関の情報管理
Open Funder Registry(研究助成機関の情報管理)サービスは、研究助成機関に一意の識別子を付与し、助成金と研究成果の関係を明確にするためのサービスです。
このデータは無料で利用でき、研究者が自身の研究に関わる資金提供者を適切に認識し、公開時にその貢献を記載することを促進します。
Reference Linking:参照リンク
Reference Linking(参照リンク)サービスは、研究論文の参考文献リストにDOIを含めることで、他の論文へのアクセスを容易にする機能です。
これにより、研究者は関連文献を迅速に見つけ、引用の正確性を確保することができます。参照リンクは、Crossrefメンバーにとっての義務ですが、他の学術機関にも推奨されています。
Similarity Check:類似性チェック
Similarity Check(類似性チェック)は、Crossrefが提供する盗用防止サービスで、Turnitinが開発したiThenticateソフトウェアを利用しています。
このサービスを使用すると、編集者は提出された論文を他の学術文献やウェブコンテンツと比較し、類似度を確認できます。Similarity Checkを利用することで、論文のオリジナリティが保たれ、学術出版の信頼性が向上します。
Cited-by:引用元
Cited-by(引用元)サービスは、学術論文が他の研究にどのくらい引用されているかを追跡する機能です。
学術コミュニティにおける研究の影響力を評価するために不可欠なサービスであり、他の研究が自分の論文を引用した際にその詳細を確認することができます。これにより、研究の広がりと影響を視覚化できます。
Metadata Plus:メタデータプラス
CrossrefのMetadata Plus(メタデータプラス)は、Crossrefのメタデータ管理機能をさらに強化したオプションサービスです。このサービスでは、APIアクセスの強化、データのスナップショット取得、優先サービスなど、より高度なデータ管理機能が提供されます。
これにより、大規模なデータ処理や詳細なメタデータ管理が可能になります。
Event Data:イベントデータ
Event Data(イベントデータ)サービスは、学術的な議論や言及がどのようにインターネット上で行われているかを追跡する機能です。
このサービスを利用することで、研究がソーシャルメディアやニュース、ブログなどでどのように取り上げられているかを把握し、その影響を評価できます。イベントデータは、研究の文脈を提供し、学術コミュニケーションを促進します。
Crossmark:クロスマーク
CrossrefのCrossmark(クロスマーク)は、論文の現在のステータス(修正、撤回、更新など)を管理し、読者に最新の情報を提供するサービスです。
論文を掲載しているサイトにCrossmarkボタンがあれば、そのボタンを押すことで、今見ている論文が最新かどうか?修正が行われたかどうか?を簡単に確認できるため、信頼性の高い情報提供が可能になります。
出版社にとってCrossrefの活用方法
DOI登録による著作物の利便性向上
DOIを登録することで、学術出版物のアクセス性が向上し、引用が容易になります。これは、出版社にとって大きな利点です。
DOIの付与により、出版物のオンラインでの発見性が高まり、研究者や読者にとって便利なアクセス手段が提供されます。
CrossCheckで守る出版倫理
CrossCheckは、出版倫理を守るための重要なツールであり、論文の盗用を防止します。
これにより、出版物の信頼性が高まります。CrossCheckを利用することで、出版プロセスにおいて不正行為を未然に防ぐことができ、学術出版の質を確保します。
Crossmarkで論文の信頼性を高める
Crossmarkを導入することで、論文が更新、修正、または撤回された際に、その情報を迅速に読者に伝えることができます。
これにより、論文が常に最新の情報を提供していることを保証し、読者の信頼を高めることができます。また、PDFなどのファイルにもCrossmarkボタンを埋め込むことで、ダウンロードされた後でも最新情報を提供できるため、コンテンツの価値を長期間維持することができます。
Open Funder Registryで研究資金の透明性を向上
Open Funder Registryは、研究資金提供者の情報を標準化して提供するサービスです。これを利用することで、出版社は論文に関与した資金提供者の情報を正確に表示でき、研究の透明性を高めることができます。
資金提供者の情報を明示することで、研究の信頼性を強化し、資金提供者からの評価も向上させることができます。
Similarity Checkで盗用防止と出版倫理の維持
Similarity Checkは、論文が他の文献とどれだけ類似しているかをチェックするサービスです。
これを活用することで、出版社は盗用を未然に防ぎ、出版物のオリジナリティを保証することができます。結果として、出版物の信頼性が向上し、出版社の評判も高まります。また、学術出版における倫理的な基準を維持するための重要なツールとして、出版社にとって欠かせないサービスです。
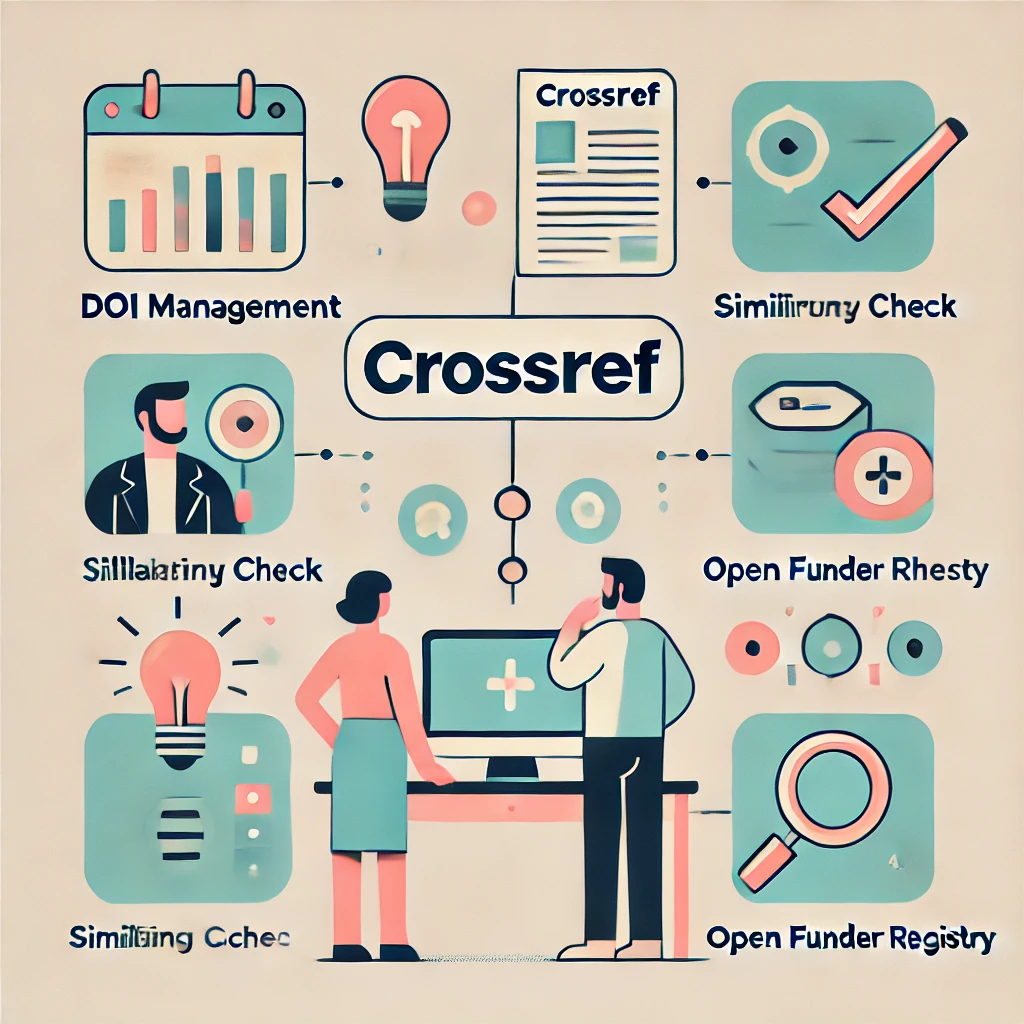
出版業界全体におけるCrossrefの採用率
Crossrefは、世界中の出版社に広く採用されており、その利用率は年々増加しています。
出版業界のCrossrefの採用率が高い理由の一つに、DOIの付与を通じて学術出版物を一意に識別し、該当の論文や学術コンテンツのアクセス性を飛躍的に向上させるその役割があります。学術出版社がCrossrefを採用することで、出版物はグローバルに認識されやすくなり、国際的な引用や参照が容易になります。
これにより、研究成果がより広範な読者層に届き、学術的な影響力が増大します。
さらに、Crossrefはさまざまなサービスを通じて、出版物のメタデータ管理、盗用防止、研究資金の透明性確保など、学術出版に不可欠な要素を網羅的にサポートしています。このような包括的なサポートが、世界中の出版社にとって大きな魅力となり、結果としてCrossrefの利用が広がっています。
また、Crossrefの普及に伴い、学術出版の標準化が進み、異なる出版社間でのデータ交換や情報共有がスムーズに行われるようになりました。これにより、国際的な研究者コミュニティ内でのコラボレーションが促進され、研究成果がより迅速に共有され、学問の進展に寄与しています。
学術出版業界のCrossrefの採用は、学術出版の質の向上と国際化を支える重要な要素となっており、今後もその影響力はさらに拡大していくと考えられます。
まとめ
Crossrefは、学術情報の流通と共有において欠かせないサービスを提供しています。
研究者や学術機関が日常的に利用しているDOIをはじめとする各種サービスは、研究成果の管理やアクセス、引用の効率化に大きく貢献しています。しかし、これらのサービスがどれほど重要であるかを、研究者の方々は普段あまり意識することなく利用しているかもしれません。
実際には、Crossrefの存在があるからこそ、世界中の学術コミュニティがスムーズに情報を共有し、知識の発展に寄与することができるのです。Crossrefは、学術出版において非常に重要な役割を果たしており、現代の学術コミュニケーションの基盤を支えていると言えるでしょう。
参考文献
- Crossref. (n.d.). Crossref Home. Retrieved from https://www.crossref.org
- Japan Link Center. (n.d.). JaLC. Retrieved from https://www.jalc.jst.go.jp
学術情報発信ラボ 執筆・編集チーム
学術サポートGr.
学術情報発信に携わる編集チームとして、長年にわたり学術出版に関する深い知識と実績を有する。国内の数十誌にわたる学術雑誌の発行サポート経験を活かし「学術情報発信ラボ」の執筆チームとして、研究者や編集者に向けた最新のトピックや、研究成果の迅速な発信に貢献する情報を発信している。
専門分野は学術出版、オープンアクセス、学術コミュニケーションであり、技術的な側面と学際的なアプローチを交えた解説が特徴。